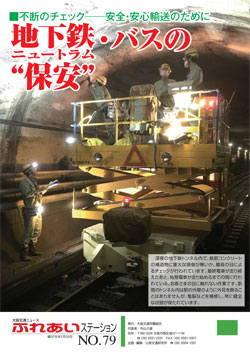 大阪交通労働組合(以下、大交)は、2月26日、大阪市営地下鉄の天王寺・なんば・梅田など、主要9駅と2つのバスターミナルで、「安心安全輸送のための保安」をテーマにした組合の政策リーフレットを配布しました。
大阪交通労働組合(以下、大交)は、2月26日、大阪市営地下鉄の天王寺・なんば・梅田など、主要9駅と2つのバスターミナルで、「安心安全輸送のための保安」をテーマにした組合の政策リーフレットを配布しました。
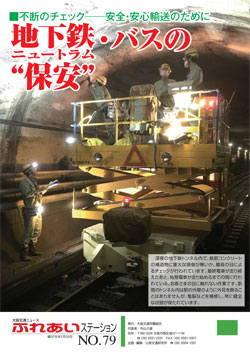 大阪交通労働組合(以下、大交)は、2月26日、大阪市営地下鉄の天王寺・なんば・梅田など、主要9駅と2つのバスターミナルで、「安心安全輸送のための保安」をテーマにした組合の政策リーフレットを配布しました。
大阪交通労働組合(以下、大交)は、2月26日、大阪市営地下鉄の天王寺・なんば・梅田など、主要9駅と2つのバスターミナルで、「安心安全輸送のための保安」をテーマにした組合の政策リーフレットを配布しました。
原発事故から5年が経過した、3月12日、福島県郡山市で開かれた「原発いらない県民大集会」で福島県大熊町の現状を大熊町役場 愛場 学さん(自治労福島県本部青年部常任委員)が報告しました。愛場さんは「大熊町が未曾有の原発事故から復興を成し遂げた町となるよう、いつか大熊町に戻り、自分にできる事を全うしたいと思う」。そして、このような過ちが、二度と繰り返されてはいけないと強調しました。
2011年3月11日に発生した東日本大震災および福島第一原子力発電所の事故により、大熊町の全域が避難指示区域となり5年が経過しました。
震災直後は、町内全域が警戒区域に指定されました。震災直後は、一時帰宅も厳しい状況でしたが、2012年12月に、年間の空間放射線量に応じて「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」の3区域に再編されました。帰還困難区域は、今も許可証がないと立ち入りできません。一方で他の2区域は、日中に限り自由に立ち入りができるようになりました。
避難により、もともと一緒に住んでいた家族が別々に生活するという状況が多く生み出されています。夫は仕事の関係で一人暮らし、妻と子どもは放射線への不安から放射線の影響のない県内外へ避難するなど、さまざまな状況によって家族が分断されているケースが多い。愛場さん家族は、避難当初、郡山市に近い三春町にある中学校の体育館に避難しました。当時、生まれて4カ月の乳児がいたため、家族は他県へ避難しました。その後、お互い離れての生活が数年続いていくうちに、家族は避難先での生活に慣れ、福島県には戻らないと決心しました。先の見えない避難生活により、もう大熊町には帰らないと決め、避難先で新たな生活を再建している人が増えています。
愛場さんのような家族がいる一方で、高齢者は住み慣れた大熊町への帰還を望んでいる方が多く、今も仮設住宅や復興公営住宅、民間アパートで生活をしています。震災前は家族で団らんし、畑仕事や散歩をすることでストレス解消になっていました。しかし、震災により家族と離れ、慣れない避難先で閉じこもりがちになり、体調を壊したり、認知症になってしまう高齢者も増えています。
長期化する避難生活の苦しみに拍車をかける問題が、中間貯蔵施設の建設です。今回の原発事故で発生した放射線に汚染された物質を数十年間保管する中間貯蔵施設の建設は、帰還の妨げとなっています。しかし、中間貯蔵施設がなければ県内外で除染した際の汚染物質の保管場所がなく、いつまでも復興は進みません。そのため、町民のなかには中間貯蔵施設の建設を容認する意見も出ています。住民は、先祖から受け継いできた土地に住めなくなるばかりか、避難の原因となった原発事故による汚染物質を保管するため、その土地を失なうという残酷な現実に迫られています。
愛場さんは「原発事故により、町民は住み慣れた土地を奪われ、地域の人間関係を壊され、家族も壊された」と語っています。しかし、「震災直後、全国の方々のあたたかい支援を受けて、凄く励まされた。そして今も、いろいろな支援を受けながら大熊町は頑張っている」。
この地域に限らず、福島第一原子力発電所事故により、今までの当たり前を全て失ってしまった住民は数えきれません。